取締役会議長・社外取締役座談会 Chairman of the Board and External Directors Roundtable Discussion
新たな経営者を迎え、更なる成長に向けて動き出した東京建物グループ。
ガバナンスの実効性向上に向けた課題について、取締役会議長と3名の社外取締役が語り合いました。
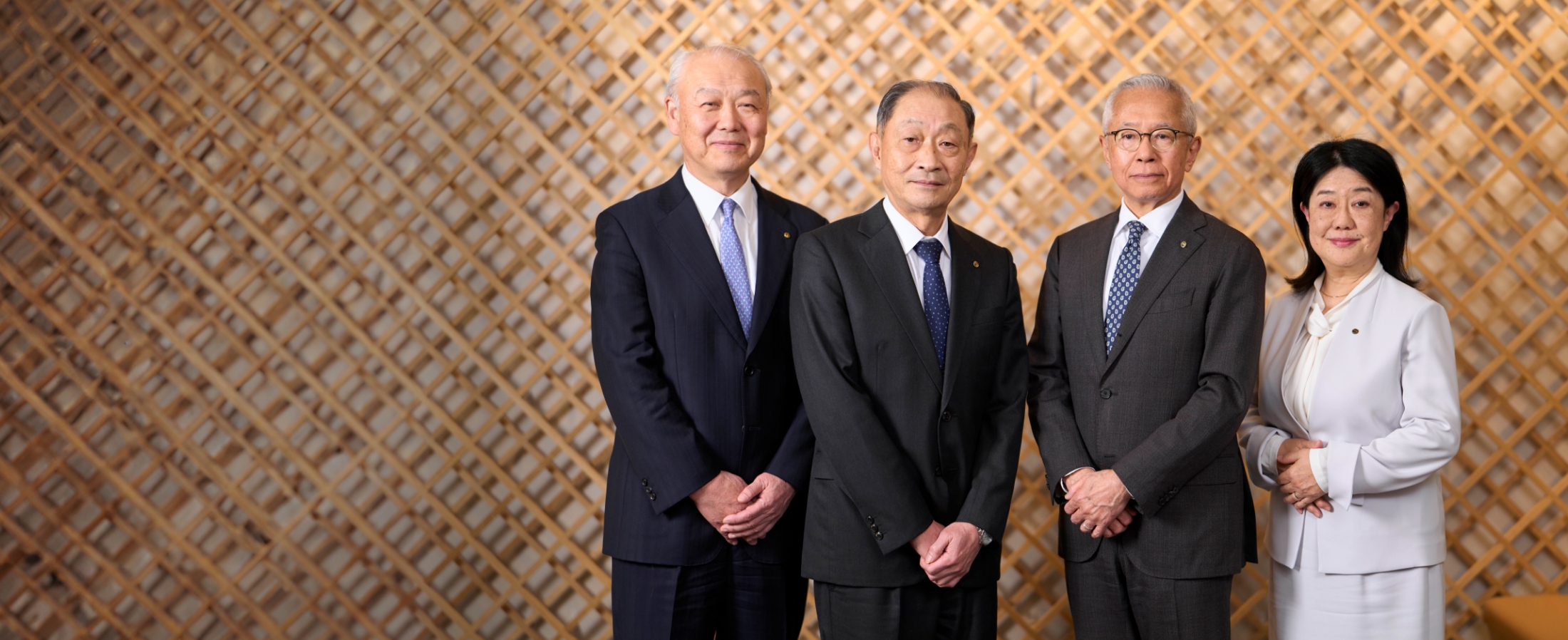
新しい経営体制のもと、
今後の持続的な成長を
支えていきます
- (左から)
-
取締役
取締役会議長 種橋 牧夫 - 社外取締役 服部 秀一
- 社外取締役 恩地 祥光
- 社外取締役 木下 由美子
社長選任プロセスの透明性について
恩地
今回の社長選任のプロセスにおいては、候補者それぞれに対して面接が行われるなど、形式にとらわれず、極めて実質的で有意義なプロセスで進んだと思います。今回は選任プロセスを通じて、候補となる方の人となりを深く知ることができた一方で、普段の取締役会などの場ではどうしても限られた一面しか見ることができていなかったこともわかり、今後の課題だと感じました。もちろん、これは社長選任に限った話ではなく、取締役会などでの議論をするうえでも互いを知っておくことは重要だと思います。例えば、執行役員や部長クラスと社外取締役のミーティングを設けることで、互いが有している仕事観やスキル、経営者としての視点などに触れられるような機会があれば、相互理解による更なる議論の活性化や将来の選任へ向けた備えもできるのではないかと考えています。

木下
選任プロセスについては恩地さんとおおむね同評価です。強いて改善点を挙げるとすれば、選任プロセスの最終スケジュールがより早く指名・報酬諮問委員会内で共有できれば、社外取締役側で質問の平仄を合わせるなどの事前準備をよりスムーズにできたと感じましたので、これは事務局にはフィードバックしました。そして、私自身が次期社長の選任に臨むにあたり重視したのは、先行きが不透明な状況下においても、一歩引いて本質を見抜く冷静さや資質を備えているか、といった点です。その観点では、指名・報酬諮問委員会における面接だけではなく、取締役会などにおいて、議論が煮詰まった局面を打開する見識などは、選任に際し参考にさせていただきました。また、小澤氏には、かつて人事部門で女性の登用に奮闘されたご経験を活かして、今後は女性やグローバル人材の積極的な活用など、長期的な視点に立った経営にも期待しています。
服部
私も今回の選任プロセスの透明性については、お二人の評価に賛同します。日本企業では、退任する経営トップが次期社長を指名する「トップダウン型」のトップ交代が多く見られますが、今回の当社のようなプロセスは私自身初めて経験しました。そして、選任に際しては、「能力」「見識」「信頼感」の3つのポイントで見るようにしましたが、最終的に社外取締役同士の議論のなかでコンセンサスが醸成されたことは、指名・報酬諮問委員会がうまく機能した結果だと思います。今後は新社長として、組織を力強く牽引し、経営の安定性と成長性の確保に努めていただきたいと思います。
種橋
皆さんのお話を聞いて、今回の社長選任においては、社外取締役による"本気の選任"が機能したことを確信しました。また、最終的な選任の判断基準として、今後当社グループが更なる成長を遂げていくために、「稼ぐ力のある人」や「勝負強さを備えた人」といった視点が重視されていたことも印象に残っています。恩地さんのお話にあったように、本年より新設された社外取締役ミーティングを活用し、執行役員、部長クラスとも接点を増やし、段階的な対話プロセスを踏んで候補者を絞り込んでいくことも重要だと思います。
中期経営計画の議論について(経営討議会の活用)
恩地
今回の中期経営計画に関する議論は、取締役会での審議を行う前に、経営討議会での議論が何度となく行われました。2023年から開始したこの経営討議会は、取締役会とは別に経営上の重要な課題などについて、中長期的な視点で幅広く議論する場ですが、当社独自の画期的な機能を持つ場と感じており、今後の継続・更なる発展を強く望んでいます。一方で、どうしても社外取締役の問いかけに対して担当役員が答える、という構図に陥りやすい課題もあります。もちろん、担当役員の立場としての回答を求めることもありますが、全社経営の視点からの意見を述べてほしい場面や、参加者同士が議論を交わしてほしい内容も多くあります。経営討議会は、むしろそうした「経営陣全体が自由に発言する場」として位置付けることで、次世代の経営人材の見極めにもつながる重要な機会としても活用できるはずです。
種橋
経営討議会における中期経営計画の議論においては、やや個別の事業計画や目標数値についての内容に偏ってしまったところがあります。この点については反省しており、今後は当社グループの将来像や新規事業の話など、未来を見据えた骨太の議論をじっくりと行える会議体へと変えていきたいと思います。なお、当社には既に「グループ戦略会議」といった会議体があり、これは新たに展開したい事業、各事業の将来展望などを議論する場と位置付けていますが、この会議体とも連携することを含め、各事業部門と社外取締役との対話を充実させていくことも重要だと考えています。

服部
経営討議会はもっと活用できるはずですね。種橋さんが指摘されたとおり、中期経営計画にかかる議論では目標数値に関する内容が中心となっていました。そのため、他の会議体ではなく、「経営討議会」で取り上げるテーマの設定としての工夫が必要かもしれません。例えば、トップダウンの視点でテーマを設定するだけでなく、社員視点で捉えた提案型のテーマもアジェンダに加えてはどうでしょうか。現場の業務に根差した発想を持った人が議論に加わることで、より現実的で創造的な成果が得られるかもしれません。M&Aについても大いに議論すべきです。M&Aに関しては、本業と地続きである場合と、本業とは違う領域の場合に分かれます。前者であれば人を派遣するなどしてハンドリングすることも可能ですが、後者の場合は難易度が高まります。そのあたりの対応については深い議論が必要だと考えています。
木下
今回の中期経営計画に対する議論は、事業別のビジネス計画をより緻密に完成させることに重きが置かれた印象があります。組織横断的に重要な人的資本の活用や、様々なリスクへの対応といったテーマについて、もう少し深く議論してもよかったのではないでしょうか。特に、人材育成・活用という点ではもう一歩踏み込みが足りなかったように思います。言うまでもなく、当社グループの今後の成長には、この分野が重要なカギを握っていますので、長期的視座にたった今後の議論と戦略の策定に期待しています。そして、事業規模の大きい競合先には発揮しえない機動性を活かして、幅広い人材の確保・育成や、DX、海外事業、M&Aなど新たな分野にも果敢に挑戦していくことが必要だと考えています。
取締役会の更なる進化に向けて
恩地
まず、当社の取締役会運営は議長である種橋さんを中心として大きく変わったと実感しています。具体的には、以前にも増して社外取締役の意見が多く取り上げられ、取締役会が実質的な議論の場としてより機能するようになったと感じます。企業の中には、取締役会での社外取締役の提言や問題提起が行われているにもかかわらず、その場だけの議論で終わったり、その取り扱いが曖昧なまま、やり過ごしたりする取締役会もまだまだあるようです。変化をしているとはいえ、当社の取締役会もようやく改善に向けた一歩を踏み出したところですので、今後は過去の提言内容やその対応状況についてきちんと整理し、取締役会の活性化に向けて課題とアクションの見える化を図ることがより大切になると思います。
種橋
同感です。特に、恩地さんが今ご指摘された「課題管理の仕組み化」は非常に重要な観点だと思います。社外取締役からの意見や提言に関し、「その後、執行側がどう対応したのかがわかりづらい」という声もあり、PDCA型の課題管理表の導入を検討したいと考えています。そうすることで、助言・提言が実現されなかった場合であっても、検討の過程を分析したり、代替案を示したりすることが可能となりますし、M&Aの議論や環境関連の案件では、具体的なリスクやコストを踏まえた議論が適正に行われたことを検証することができます。
木下
お二人とは少し違った角度からの要望となりますが、当社が手がけている事業の物件見学会や勉強会もぜひ企画していただきたいですね。こうした経験は社外取締役としての事業理解にもつながり、取締役会での議論の質を高めるうえでは重要だと考えています。また、議論のテーマとして、サステナビリティ経営に関しては社外取締役を交えた深い議論に至ることが少ないように思います。今はサステナビリティ委員会からの報告という形でその活動状況や課題などについては一定程度把握できていますが、戦略的な課題の洗い出しや本質的な議論が足りていない印象があります。経営討議会や社外取締役ミーティングを活用しながら、先ほども触れたような、人材戦略やリスク管理の強化といった具体的なテーマについて深い議論ができればよいと思います。

服部
私はすでに10年、当社に関わってきていますが、当社取締役会の位置付けが近年、加速度的に変わりつつあると感じています。かつては、ある意味では「投資判断のための議論の場」という側面を強く感じていましたが、現在は取締役会議長のもと、経営を忌憚なく議論する場へと進化してきているように思えます。こうした議論の質の向上を含め、各会議体をいかにして有効に機能させていくかが、ガバナンスの実効性向上につながっていくのではないかと考えられます。
今後の持続的成長に向けた期待
恩地
当社は前中計期間中に十分な成長を遂げたと思いますが、今後の更なる持続的成長に向けては、M&Aによる成長や新規事業の機会を拡大させるべく、情報収集の機能強化やそれらを専門的に検討する社内体制の整備も重要になってくると思います。また、成長戦略の基盤となる事業ポートフォリオ戦略についても、一考の余地があると考えています。オフィスビルやマンションといった中核事業に加え、今後の成長が期待されるサービス領域や新規事業、関連会社での事業についても、それぞれの特性に応じて、業界内でのポジションや長期的な目標を明確にし、戦略の策定と進捗管理を徹底することが求められる時期に来ているのではないでしょうか。
服部
事業ポートフォリオ戦略の議論は継続的に行っていくべきですね。中長期スパンのビジネスを展開し、長期のリスクを取っていく当社グループのような企業にとって、事業ごとにリスクファクターが異なる事業を自社のポートフォリオとして持つことは重要な意味を持ち、結果的に投資家の利益に貢献できると考えています。

木下
中長期的な成長、という観点で言えば、当社グループならではの強みである「信頼」に根差した企業カルチャーを継承していくことが重要で、例えば、企業カルチャーの言語化や企業ミッションの策定も本格的に検討していく必要があるかもしれません。また、経営環境の不透明さが加速する中で、現状の延長線上にある積み上げの事業計画だけではなく、あるべき姿からバックキャストして新しい分野に挑戦するための柔軟な発想を持つことも大切だと思います。
種橋
本日は皆さんからの多様かつ貴重な示唆をいただきましたが、新たな経営体制での中期経営計画もスタートしたところとなりますので、今後もより一層、執行サイドと取締役会が相互に理解を深め、実効的な議論を行うことで、戦略の着実な実行、当社グループの持続的成長の実現をサポートできればと考えています。

種橋
経営トップの選任に際しては、適切な選任プロセスが踏まれたか、指名・報酬諮問委員会※がいかに機能したかといった点が投資家から注目されるポイントだと認識しています。今回の選任にあたっては指名・報酬諮問委員会で、候補者にこれまでの業務経験を踏まえた強みや、自らの経営理念、会社の将来展望を語っていただき、それに対して質疑を行いました。新社長選任プロセスという観点で、社外取締役の皆さんはどうお感じになられましたか。
※2025年から指名・報酬諮問委員会を「指名諮問委員会」と「報酬諮問委員会」に分離